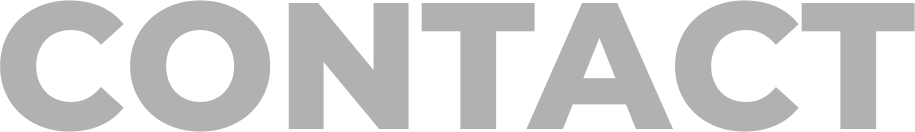ライティングフレームワーク完全ガイド|PREP法やPASONA法など代表的な8型を例文付きで一挙解説
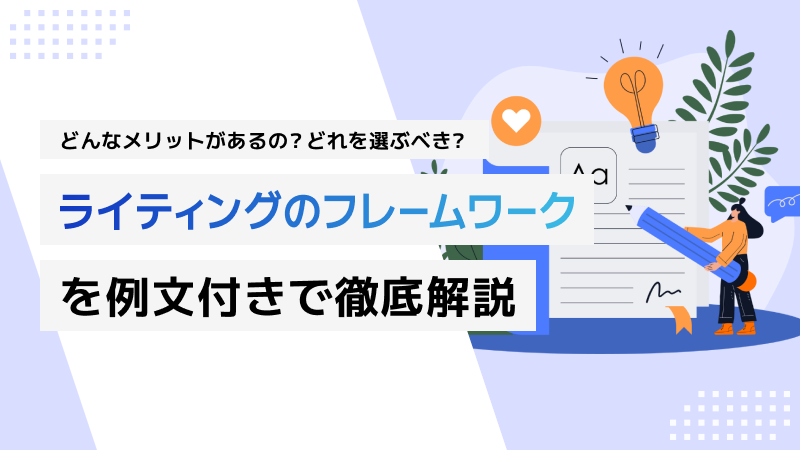
ライティングフレームワークとは
ライティングフレームワークとは、文章の構造を「テンプレート=型」として先に決めておくことで、誰でも再現性高く説得力のある文章を書けるようにする仕組みです。
たとえば PREP法なら〈結論→理由→具体例→もう一度結論〉の順で並べるだけで、初学者でもロジックの抜け漏れなく主張できます。型に沿って書くことで構成に悩む時間が減り、校正者もチェックポイントが明確になるため修正スピードも上がります。
歴史と背景
広告コピーの黎明期だった1960年代にAIDMAやFABといった「購買心理」を反映した型が生まれ、その後 IT バブル期にはPREPが技術系ブログやニュース記事で定番化しましたSNSとスマホが一般化した2010年代以降は、煽り要素を抑えつつ共感を呼ぶ PASO・PASONAなどがLPで多用され、現在はAIライティングツールの普及でOATH・QUESTのように「読者の心理段階を細かく区切る型」が再注目されています。時代ごとに媒体と読者の行動が変化し、それに合わせてフレームワークも進化してきたわけです。
導入メリット
まず時間短縮の効果が大きく、社内アンケートでは「構成に悩む時間が従来の3分の1になった」という声が多数上がります。さらに説得力向上も見逃せません。主張と根拠、事例を整理して配置できるため、同じ商品説明でもCTAのクリック率向上が期待できます。また、大きなメリットとしては検証と改善のしやすさです。文章をセクション単位でABテストできるため、データを基に「どの段落を入れ替えるか」などの改善が容易になります。
ライティングのフレームワークを活用すべき人とは
BtoB企業で毎月大量の記事を公開する Web担当者や、LPを短期間で量産しなければならないマーケティング担当者にとって、フレームワークは必須の武器となります。新人ライターや外部ライターにも型を共有しておけば、校正回数が減り制作コスト全体の圧縮にもつながります。
次章では、代表的な8種のフレームワークを「構成要素・得意分野・代表的な強み」で比較し、読者が自分の目的に合った型を選べるよう徹底的に整理します。
主要8フレームワーク徹底比較

文章の型は数多くありますが、本記事では 「ビジネスライティングで再現性と効果が実証されている8種」 に絞って解説します。比較軸は以下の3つです。
- 1.構成要素
- 2.得意分野
- 3.代表的な強み
まず俯瞰表で全体像を頭に入れてから、各フレームワークの特長を順に深掘りしていきましょう。
| フレームワーク | 構成要素(頭文字) | 得意分野 | 代表的な強み |
|---|---|---|---|
| SDS | Summary / Detail / Summary | ブログ冒頭・要約 | 離脱防止と記憶定着 |
| PREP | Point / Reason / Example / Point | 社内報・解説記事 | ロジックの一貫性 |
| PASO | Problem / Agitation / Solution / Outcome | LP・セミナー告知 | 危機感と達成感の両立 |
| PASONA | Problem / Agitation / Solution / Narrowing / Action | ステップメール | セグメント訴求力 |
| AIDMA | Attention / Interest / Desire / Memory / Action | 広告コピー | 心理曲線を段階的に操作 |
| QUEST | Question / Understanding / Education / Stimulate / Transition | SNS長文ポスト | 共感と教育のハイブリッド |
| FAB | Feature / Advantage / Benefit | 商品紹介ページ | 即時ベネフィット提示 |
| OATH | Oblivious / Apathetic / Thinking / Hurting | 高単価商材LP | 潜在課題を顕在化 |
SDS法―要点と詳細を往復し、読者の離脱と理解漏れを同時に防ぐ
SDSは最初に結論を示し、続いて詳細を整理し、最後にもう一度結論へ戻る3ブロック構成です。
冒頭で全体像を提示すると読者は安心して読み進められ、中盤で得た情報を終盤で再確認することで記憶への定着も高まります。要約部は20〜30行に抑えると視線の滞留を防げ、詳細部では事実と解釈を段落単位で分けると論点が交錯しません。再要約では先に示した結論を言い換えつつ未来の提案を添えると付加価値が生まれ、読み終えた直後に行動イメージが浮かびやすくなります。
大きな特徴は短時間で核心を掴ませる点にあり、速報記事や部門横断共有のサマリー資料に適性があります。一方、詳細部の情報整理が甘いと再要約が弱くなるため、段落ごとの論点管理が必須です。
PREP法―主張・理由・具体例の順序で納得度と再現性を最大化
PREP法は結論を先に提示し、理由で論理を示し、具体例で裏づけを行い、最後に結論を繰り返します。
読者は初動でテーマを理解し、その後に根拠と実証をたどるため一貫した思考体験を得られます。理由には因果関係を示す接続語を置き、具体例には数値や比較情報を入れると説得力が大幅に増します。再結論では行動指針を一文追加すると読後の迷いを断ち切れます。
型自体がシンプルなため執筆スピードが向上し、校正基準も明確になります。注意点は理由が抽象的だったり例示が曖昧だったりすると再結論が空疎に感じられることで、エビデンスは必ず数値や一次情報で補強する必要があります。
PASO法―危機感を高め、解決後の成果を描いて行動へ導く
PASO法はProblemで課題を提示し、Agitationで感情を揺さぶり、Solutionで解決策を示し、Outcomeで成果を具体的に描きます。
最大の強みは読み手に危機感と安心感を同時に与えられる点です。問題提示では共感できる実情を描写し、煽りで機会損失や時間損失を可視化して緊急度を上げます。解決策は手順と効果を両面から提示し、成果では導入後の姿をイメージしやすい言葉で背中を押します。
バランスを誤ると煽りが過剰になり不信感につながるため、客観データを挟んで根拠を補強するのがポイントです。
PASONA法―絞り込みで共感を深め、段階的に行動へ背中を押す
PASONA法はPASO法の流れにNarrowingとActionが加わり、ターゲットを特定してから具体的行動を促します。
絞り込みフェーズでは対象読者の業種や役職を明示し、自分事化を強化します。これにより問題意識が鮮明になり、提示する解決策が自分に合った答えとして響きやすくなります。行動パートでは複数オファーを段階別に用意し、低ハードルのCTAから高ハードルへ誘導すると離脱を抑えながら成果を伸ばせます。
ただし絞り込みが曖昧だと刺さらないため、ペルソナ設定やセグメント分析を事前に行い対象を具体化しておくことが重要です。
AIDMA法―五段階で欲求曲線を描き、短文でも強い行動喚起を実現
AIDMA法はAttention、Interest、Desire、Memory、Actionの順で読者心理を段階的に刺激します。
短文コピーでも心理曲線を緻密に設計できるため、広告バナーやテキスト広告のように文字数が限られる媒体で威力を発揮します。注意を引くフレーズでは数字や疑問形を置き、興味フェーズではメリットを簡潔に提示します。欲求フェーズでベネフィットを強調し、記憶フェーズでブランド名や主要ワードを反復して残存率を高め、最後に行動を明確に指示します。
段階を飛ばすと流れが不自然になるため、5要素を必ず順守することが成功条件です。
QUEST法―質問と教育を重ね、共感を維持しながら行動へ導く
QUEST法はQuestion、Understanding、Education、Stimulate、Transitionの五段階で構成され、疑問提起から教育的情報提供までを一気に行う点が特徴です。
まず読み手の疑問を言語化して共感を獲得し、その疑問に対する理解を深める情報を提示します。続く教育フェーズで新たな気づきを与え、刺激フェーズで感情を揺さぶる事実や比喩を差し込み、最後に行動へ移す設計です。
長文でも飽きさせない秘訣は教育パートに図解やチェックリストを挟み、情報密度と可読性を両立させることにあります。
FAB法―機能がもたらす利点を利益へ翻訳し、購買決定を加速
FAB法はFeature、Advantage、Benefitの順で説明し、読者が製品機能を見た瞬間に自分のメリットを想像できるようにします。
機能を列挙するだけでは差別化に繋がりませんが、利点を経由して最終利益へ落とし込むことで導入後の具体的な変化をイメージさせられます。利点を示す際には競合比較や定量データを使い、利益パートでは読者の生活や業務がどう改善されるかを描写すると説得力が飛躍的に高まります。
OATH法―潜在課題を段階的に自覚させ、高単価商材の壁を越える
OATH法はOblivious、Apathetic、Thinking、Hurtingの四段構成で、課題認知の浅い読者を痛みの自覚まで導きます。
無関心段階では課題の存在を提示し、無感情段階では影響を具体的に描写します。思案段階で費用対効果を示し、痛み段階で放置リスクを明確にして導入の必然性を高めます。
ネガティブ情報に偏りすぎると拒否反応を招くため、解決後のポジティブな未来像を並置して読者の想像を前向きに誘導しましょう。
主要8フレームワークのサンプル文章紹介

この章では、紹介した8つのフレームワークを使った文章例を紹介します。実際の利用シーンをイメージできるように、複数のケースを想定して文章を作成しました。実際の業務をイメージしながら読んでみてください。
SDS法のサンプル文章4パターン
SDS法は「要約→詳細→再要約」という3段階で構成されるもっともシンプルな型です。最初に結論を明示するので、読む前に全体像が分かり安心感を与えられます。続く詳細パートで根拠や背景を丁寧に補足し、最後に要点をもう一度まとめることで情報が記憶に残りやすくなります。ニュース記事の冒頭や社内報告書のサマリーなど、短時間でポイントだけ押さえてほしい場面に最適です。読者は冒頭と末尾を読むだけでも内容を把握できるため、離脱率を下げつつ理解度を高める効果があります。
パターン1. クラウドストレージサービスの紹介文
新しいクラウドストレージは、社内外どこからでも安全にファイル共有できる点が最大の特長です。転送速度を最適化するキャッシュ機能と、ゼロトラスト認証を組み合わせた高いセキュリティを備えており、導入初日から既存システムにほとんど手を加えず運用を開始できます。さらに、管理画面はアクセス権限をドラッグ操作で設定できるため、IT部門の負荷も抑えられます。つまり、このサービスを使えばセキュリティリスクを増やさずにファイル共有の手間とコストを同時に削減できます。
パターン2. SEO記事のリード文(Bluetoothとは?)
Bluetoothは、ケーブルを使わずに機器同士を接続できる近距離無線通信規格です。スマートフォンとワイヤレスイヤホンが自動でペアリングする仕組みを支えているのがこの技術で、通信距離は約10メートル、消費電力が低い点が強みとして挙げられます。規格はバージョンアップを重ねており、最新世代では音質と通信速度がさらに向上しました。結論として、Bluetoothは日常の小さなストレスを解消し、モバイル体験を快適にする必須テクノロジーです。
パターン3. オンラインセミナー告知文
来月開催する無料オンラインセミナーでは、生成AIを活用したマーケティングオートメーションの最新事例を解説します。講師は実務歴15年のコンサルタントで、導入プロセスからROIの測定方法まで具体的なノウハウを共有する予定です。当日は質疑応答の時間も設けており、自社課題を直接相談することが可能です。参加登録は所要1分、定員500名のため関心のある方は早めに申し込んでください。
パターン4. 社内報のプロジェクトサマリー
第二四半期に開始した在庫管理システム刷新プロジェクトは、予定通り要件定義フェーズを完了しました。現行システムとの連携テストで想定外のタイムラグが見つかりましたが、ミドルウェア設定を変更することで解決し、今後の進行に大きな影響はありません。来月からは画面デザインとユーザビリティテストに入る予定で、全社員を対象としたフィードバックアンケートを実施します。プロジェクトは現在スケジュール・コストともに計画どおりで推移しているため、正式リリースは当初予定の10月を維持できる見込みです。
PREP法のサンプル文章4パターン
PREP法は「結論→理由→具体例→再結論」の順番で話を進める王道のロジカルライティングです。最初に言いたいことを提示し、すぐに理由を説明するため読者は筋道を追いやすくなります。その後、実際の数字や事例を示すことで納得度が大幅にアップし、最後にもう一度結論を繰り返すことで印象を強めます。
PREP法は、レポートや技術解説記事、社内稟議など説得材料が求められる文章と特に相性が良いフレームワークです。構成が決まっているため執筆スピードも速く、チームで品質をそろえたいときにも重宝します。
パターン1. サブスクリプション管理ツールの訴求文
結論:サブスクリプション管理ツールを導入すべきです。
理由:請求漏れの防止と解約率の低減を同時に実現できるからです。
具体例:導入企業では請求処理が自動化され、カスタマーサクセスの工数が大幅に削減されています。
再結論:したがって、本ツールはキャッシュフローを安定させながら顧客満足度も高める最適な選択です。
パターン2. SEO記事リード文(Bluetoothとは?)
結論:Bluetoothは日常生活を快適にする近距離無線通信規格です。
理由:ケーブルを使用せずに機器同士を接続でき、省電力かつ汎用性が高いからです。
具体例:スマートフォンとイヤホンの自動ペアリングやワイヤレスキーボードの接続が代表的な活用例です。
再結論:つまり、Bluetoothはモバイル体験の利便性を飛躍的に向上させる基盤技術と言えます。
パターン3. 採用イベント告知文
結論:オンライン会社説明会に参加すると、ご自身のキャリアの幅を大きく広げられます。
理由:現場責任者が事業戦略や評価制度を直接解説し、さらにリアルタイムの質疑応答で疑問点をその場で解消できるからです。
具体例:参加者はプロダクトのロードマップを詳しく理解したうえで選考に進み、面接準備の不安を減らしています。また、会社のカルチャーを動画で確認できるため、入社後のギャップが小さくなる点も好評です。事前に提出できる質問フォームを活用すれば、当日の回答精度が高まり、限られた時間を最大限有効に使えます。
再結論:そのため、成長機会を求めているエンジニアやマーケターの方は、ぜひこの説明会にお申し込みください。参加登録は短時間で完了し、視聴リンクは自動送付されるため、準備の手間もかかりません。
パターン4. 社内稟議書サマリー
結論:営業支援ツールの導入を承認いただきたく存じます。
理由:現在、商談情報の可視化が遅れており、機会損失とレポート作成の工数増加が発生しているためです。
具体例:試験導入では案件状況をリアルタイムで共有できた結果、営業会議の準備時間が短縮され、マネージャーはデータ分析に集中できました。さらに、担当者間で重複提案が発生しなくなり、顧客対応の質が向上しています。ツールは既存SFAとAPI連携が可能であるため、移行コストを抑えつつ運用を開始できます。利用料は月額固定で、導入後のメンテナンス負荷も軽微です。
再結論:以上より、本ツールは売上向上と業務効率化の双方に寄与する投資と判断いたします。ご承認のほど、よろしくお願いいたします。
PASO法のサンプル文章4パターン
PASO法は「問題提起→感情喚起→解決策→結果提示」の流れで読者の不安と期待を同時に刺激します。最初に課題を示し、放置するとどんな損失が生じるかを想像させることで危機感を高めます。続いて具体的なソリューションを提示し、その施策によって得られるポジティブな未来像を描くことで行動の背中を押します。
ランディングページやイベント告知のように、短い導線で申し込みまでつなげたい場合に効果的です。煽りすぎないよう第三者データや客観的な根拠を添えると信頼性が向上します。
パターン1. クラウドバックアップサービス紹介文
業務サーバーの障害が発生した場合、最新データを失う恐れがあります。復旧が遅れれば取引先への納期遅延や信頼低下が加速します。クラウドバックアップサービスを導入すれば日次で完全自動保存され、復元も数クリックで完了します。結果としてダウンタイムを最小化し、顧客対応や社内作業を止めずに事業を継続できます。
パターン2. SEO記事リード文(社内eラーニング活用)
社員研修が動画の視聴だけで終わり、学習定着が進まないことが課題です。そのままでは教育コストが増える一方でスキルギャップが残り、生産性が伸びません。インタラクティブ型eラーニングを採用すると、クイズやシミュレーションで理解度を即時測定できます。研修後のレポートで弱点を把握できるため、再教育の的確さと学習効果の向上が同時に達成できます。
パターン3. 製造業向け予知保全ツール紹介文
突発的な機械停止は生産ライン全体の遅延を引き起こします。予定外の停止が続くと納品遅延による違約金リスクが増大します。予知保全ツールを導入して振動や温度データをリアルタイム監視すれば、故障兆候を事前に検出できます。結果的に計画停止へ切り替えられ、保守コスト削減と製品出荷の安定を確保できます。
パターン4. オンラインフィットネスプログラム告知文
在宅勤務が続き、腰痛や肩こりに悩む人が増えています。放置すると集中力の低下や長期的な健康リスクが高まります。オンラインフィットネスプログラムでは自宅でできるストレッチと筋力トレーニングを週3回ライブ配信します。継続参加により姿勢改善と疲労軽減が期待でき、業務効率も向上します。
PASONA法のサンプル文章4パターン
PASONA法はPASO法をベースに「絞り込み」と「行動喚起」を加えた5段階構成です。問題と解決策を提示したあとで、対象読者を具体的に指名することで自分ごと化を強めます。
たとえば「製造業のDX担当者の皆さま」と呼びかけるだけで共感度が格段に上がります。最後に行動を誘導するCTAを設置し、無料相談や資料ダウンロードなどハードルの低い選択肢から導くと成果が取りやすくなります。メールマーケティングやセールスレターで高反応を狙いたいときに最適な型です。
パターン1. リード獲得ホワイトペーパー告知文
自社サイトへの訪問者が資料請求まで進まないことが課題です。放置すれば広告費だけが増え続け、営業パイプラインが細る恐れがあります。解決策として、導入事例を中心に構成したホワイトペーパーを無償提供し、価値と具体的手順を先に提示します。製造業でDXを担当する管理職の方に向けて作成しているため、課題の全体像からROI計算方法まで一気に把握できます。今すぐダウンロードフォームからメールアドレスを登録してください。
パターン2. BtoBウェビナー招待メール
営業メールに反応がなく、商談数が目標を下回っていることが問題です。そのまま月次目標を達成できない状態が続けば、部署全体の評価に影響します。オンラインウェビナーでは、失注要因を分析するチェックリストと改善手順を実演付きで解説します。製品の選定権を持つ情報システム部長の方に向けて設計しているため、明日から実行できる内容に絞っています。参加リンクは定員制ですので、今週中にお申し込みください。
パターン3. サービス紹介LPの導入部
新しいチャットボットを導入しても顧客満足度が向上しないという声が増えています。対応履歴が分析できず、応答品質の改善サイクルが止まることで機会損失が拡大する可能性があります。当社の対話型AIプラットフォームは、ユーザーの質問意図を自動タグ付けし、改善ポイントをダッシュボードで可視化します。ECサイトで顧客対応を担当するマネージャーの方に最適化されており、シナリオ編集もノーコードで完結します。資料請求はフォームに会社名とメールアドレスを入力するだけで完了します。
パターン4. 社内向け業務改善提案書サマリー
経費精算の処理が紙ベースで行われ、承認待ちが滞留する状況が続いています。このままでは月末に稟議が集中し、残業コストが増加するリスクが高まります。ワークフローシステムを導入すれば、申請から承認までをオンライン化し、進捗をリアルタイムで追跡できます。経費申請の承認権限を持つ課長職以上の方に向けて導入手順と試算シートをまとめました。試験導入チームの募集を来週金曜まで受け付けていますので、ご協力をお願いします。
AIDMA法のサンプル文章4パターン
AIDMA法は広告理論で有名な「注意→興味→欲求→記憶→行動」の5段階モデルです。まず目を引くキャッチコピーで注意を集め、読者にメリットを示して興味を引きます。その後「自分にも必要だ」と思わせる欲求を喚起し、ブランド名や商品名を繰り返して記憶に定着させ、最後に行動を具体的に指示します。
文字数が限られるバナー広告やポップアップでも使いやすく、短文でも読者の心理を段階的に動かせるのが強みです。段階を飛ばすと不自然になるので、5要素を順番通りに入れることが成功のポイントです。
パターン1. SaaS体験版バナーコピー
Attention: 今だけの特典としてクラウドタスク管理ツールTaskFlowの30日無料体験版を配布しています
Interest: ブラウザからログインするだけでプロジェクト全体の進捗をリアルタイム共有できるため在宅勤務でも情報が途切れません
Desire: 初期設定ウィザードを使えばチームメンバーの登録と権限付与が5分で完了し導入当日から本格運用が始められます
Memory: 快適なタスク管理をかなえるTaskFlowという商品名をぜひ覚えてください
Action: 体験版ページにアクセスしメールアドレスを入力してアカウントを作成し活用メリットを実感してください
パターン2. ECサイトメールマガジン冒頭文
Attention: 高音質ワイヤレスイヤホンSoundNextProの先行販売が本日スタートしました
Interest: 新開発のドライバーが低音域を強化し通勤ラッシュの車内でもクリアなサウンドを楽しめます
Desire: 片耳4gの超軽量設計なので長時間のオンライン会議でも耳が痛くならず集中力を維持できます
Memory: 製品名はSoundNextProでカラーはブラックとシルバーの2種類をご用意しています
Action: 下記リンクから商品ページへ進みカートに追加して限定特典のポーチを受け取ってください
パターン3. 店舗ポスターコピー
Attention: 9月限定でランニングシューズ全品20パーセントオフのキャンペーンを開催しています
Interest: 独自開発のソールが着地衝撃を30パーセント吸収し膝への負担を軽減します
Desire: ビギナーでも正しいフォームを促す設計なので毎日のジョギングが習慣化しやすく目標達成を後押しします
Memory: 会計時にキャンペーンコードRUN24を提示するだけで割引が適用されます
Action: 試し履きコーナーでフィット感を確認しレジでRUN24を伝えてお得に購入してください
パターン4. モバイルアプリプッシュ通知
Attention: 英語学習アプリWordStepからのお知らせです 今日の学習目標が未達成のままです
Interest: クイズ形式の反復練習で単語を短時間に定着させ次回テストで点数アップを狙えます
Desire: ゲームのようなレベル制なので通勤中や休憩時間の3分でも楽しく継続できます
Memory: 学習履歴はクラウド保存され進捗レポートを週次で確認できるWordStepを忘れないでください
Action: 画面をタップしてアプリを開き本日のクイズ5問に挑戦し連続学習記録を更新してください
QUEST法のサンプル文章4パターン
QUEST法は「質問→理解→教育→刺激→移行」という流れで、読み手との対話を意識した構成になっています。最初に疑問を投げかけ共感を得たうえで、その疑問を解くための知識を分かりやすく提供します。続いて新しい視点やデータで刺激を加え、最後に具体的アクションへ誘導する設計です。
長めのSNS投稿やコラム記事で、読者に学びと感情の両方を与えながら行動させたいときに効果的です。最後まで文章を読んでもらうために、教育パートは図や箇条書きを交えると読み疲れを防ぐのに効果的です。
パターン1. オウンドメディア記事導入文
Question: あなたの企業サイトは訪問数が増えても問い合わせにつながらないと感じていませんか
Understanding: 多くのBtoB企業ではトップページに製品情報が散在し導線が複雑になっています
Education: 本記事では導線を一本化する内部リンク設計とユーザビリティテストの進め方を詳しく解説します
Stimulate: 記事を読み終える頃には問い合わせ率が向上するサイト構造を自社で再現できるイメージが湧きます
Transition: まずはチェックリストをダウンロードして自社サイトの現状を確認してください
パターン2. SNS長文ポスト
Question: 新しい業務ツールを導入しても社内に浸透しないのはなぜでしょうか
Understanding: 多くの導入失敗は初期設定よりも活用シナリオの不足に起因します
Education: 浸透を成功させた企業は運用ガイドとKPIを導入初期から並行して作成し定着を支えています
Stimulate: あなたのチームでも同じ仕組みを取り入れることで社内の抵抗感が減りROIが可視化されます
Transition: コメント欄のリンクからテンプレートを入手し今週中にガイドラインを作成してみてください
パターン3. メールマガジン本文
Question: 顧客アンケートの回収率が想定より低く改善案に行き詰まっていませんか
Understanding: 回収率が伸びない主因は設問数の多さと回答メリットの不明確さにあります
Education: アンケートを三段構成に整理し回答特典を明示すると平均回収率が二倍以上に伸びるケースが多く報告されています
Stimulate: この改善を行えば顧客の本音が集まり製品開発のスピードと精度が高まります
Transition: 同封のチェックリストを参考にアンケート設計を見直し次回配信で効果を検証してください
パターン4. ウェビナーランディングページ冒頭
Question: 社内データを活用したいのに可視化ダッシュボードがうまく機能しないと悩んでいませんか
Understanding: 可視化が失敗する要因は定義が統一されていないKPIが多すぎることです
Education: ウェビナーではBIツールに適した指標設計とデータガバナンスの基本を基礎から説明します
Stimulate: 受講後は複雑なデータでも一目で意思決定ができるダッシュボードを自社で構築する手順が理解できます
Transition: ページ下部の申し込みフォームから日程を選択して参加登録を完了してください
FAB法のサンプル文章4パターン
FABは「機能→利点→利益」の3段階で製品価値を伝えるシンプルな型です。まず製品が備える具体的な機能を示し、その機能がもたらす利点を説明したあとで、最終的にユーザーが得られる利益を描写します。読者は自分にとってのメリットをすぐ理解できるため、購買までの心理的距離が短くなります。
ECの商品説明や提案書に使うと、機能説明に終始せずメリット・ベネフィットまで伝えられるので説得力がアップします。利益を示す際は時間短縮やコスト削減など具体的な数値を入れると効果的です。
パターン1. スマートサーモスタット紹介文
Feature: AI温度学習アルゴリズムが室内外の温度変化を常時解析します。
Advantage: 自動で最適設定に切り替わるため手動調整の手間がなく、無駄なエネルギー消費を抑えられます。
Benefit: 月々の光熱費が下がりつつ、帰宅した瞬間から快適な室温が保たれるので家族全員が快適に過ごせます。
パターン2. 分析ダッシュボードSaaS訴求文
Feature: リアルタイムストリーミング処理により秒単位でデータを取り込みます。
Advantage: 集計を待たずに最新数値を確認できるため分析作業が中断されません。
Benefit: 意思決定が迅速になりトレンド変化への対応が早まることで機会損失を防げます。
パターン3. HRオンボーディングソフト紹介文
Feature: テンプレート済みワークフロービルダーを搭載し、業務手順をドラッグ操作で組めます。
Advantage: コーディングや複雑な設定が不要で、人事担当者が自力で自動化を完結できます。
Benefit: 新入社員が必要資料を迷わず受け取り早期に戦力化できるため、定着率が向上し人事部の負担も軽減します。
パターン4. ポータブルソーラーチャージャー告知文
Feature: 折りたたみ式で高効率の単結晶パネルを採用しています。
Advantage: バッグに収まるサイズながら日照があれば短時間でスマートフォンをフル充電できます。
Benefit: キャンプや停電時でも電源を確保できる安心感が得られ、屋外アクティビティの自由度が高まります。
OATH法のサンプル文章4パターン
OATHは「無関心→無感情→思案→苦痛」の4ステージで潜在課題を顕在化させ、高単価商材への導入意欲を醸成します。まず課題自体に気付いていない状態から、徐々にその影響を具体的に示して関心を高めます。思案ステージでは費用対効果や実行手順を提示し、最後に課題を放置した場合のリスクを明確にすることで行動を後押しします。
検討期間が長くなりがちなBtoBや高額サービスで特に有効です。恐怖訴求に傾きすぎないよう、解決後のポジティブな未来像を合わせて描くとバランスが取れます。
パターン1. エンタープライズ向け脆弱性診断サービス
Oblivious: 社内システムが最新の攻撃手法にさらされている事実をまだ認識していません。
Apathetic: 最近ニュースで取り上げられる情報漏えいも自社には関係ないと考えがちです。
Thinking: しかし、社員数が増えるにつれてアクセス権管理が煩雑になり、このままで良いのかと疑問を抱き始めています。
Hurting: 万一の侵害時には顧客データが流出し、信頼と売上の両方を失うリスクが大きいと気づき、不安が現実味を帯びています。
パターン2. 高単価デジタルマーケティング講座のLP導入文
Oblivious: 広告運用を自社担当者に任せきりで、収益が伸び悩む原因を把握していません。
Apathetic: コンバージョン率が横ばいでも業界全体が厳しいから仕方ないと半ば諦めています。
Thinking: 一方で、競合が新しい施策を次々と打ち出す様子を見て漠然とした焦りを感じ始めています。
Hurting: 現状を放置すれば広告費だけが膨らみ、来期の予算確保すら難しいという危機が具体的に見えてきています。
パターン3. 製造業向け省エネ改修コンサルティング提案文
Oblivious: 設備の老朽化が進んでいるにも関わらず、電力量の詳細な測定を行っていません。
Apathetic: 電気代が年々上がっても原材料費の高騰に比べれば小さいと判断し、改善を後回しにしています。
Thinking: ただ、ESG評価の提出が求められ始め、エネルギー効率の見直しが避けられないことを感じ取っています。
Hurting: 放置すれば環境規制への対応遅れが取引停止につながる可能性が高まり、経営リスクとして顕在化しています。
パターン4. キャリアコーチングプログラム紹介メール
Oblivious: 業務量は多いのに成果が見えづらく、キャリアプランを立てていない状況です。
Apathetic: いつか転職したいと考えるものの、具体的な行動を起こさず日々のタスクをこなすだけになっています。
Thinking: 同期が昇進や転職で活躍の場を広げる姿を見て、自分も変わるべきではないかと考え始めています。
Hurting: 動かなければ今後も評価が上がらず、将来の年収や働き方を自分で選べないという危機感が強まっています。
ライティング目的別フレームワークの選定方法

この記事の後半では具体例を提示しましたが、実際に執筆へ落とし込む段階で「どの型を選ぶべきか」で迷ってしまうことは少なくありません。この章では目的・読者理解度・媒体の3軸でフレームワークを絞り込む手順を整理します。
以下のステップに分けて見ていきましょう:
1. 目的を定義して優先順位を明確にする方法
2. 読者の理解度を分類し想定シナリオを具体化する手順
3. 目的×理解度で推奨フレームワークを決定するガイド
順番に解説します。
ステップ1. まず目的を決める
文章づくりで最初に迷いやすいのが「けっきょく何を達成したいのか」というゴール設定です。ここがはっきりしないと、どのフレームワークを当てはめても効果がぼやけてしまいます。まずは、下の4つの目的から「これだ」と思えるものを必ず1つ選びましょう。
| 目的 | やること・ゴールイメージ |
|---|---|
| 認知拡大 | 名前やトピックをまず知ってもらう段階。SNSシェアやブランド検索が増えれば成功。 |
| 興味喚起 | 読者に「自分ごと」と感じてもらう段階。ページ滞在や内部リンククリックが伸びれば成功。 |
| 行動促進 | 資料請求や無料相談など“最初の一歩”を踏ませる段階。CTAクリックが指標。 |
| 販売クロージング | 契約や購入を背中押しする段階。申込完了が指標。 |
初心者が迷いやすいQ&A
Q1: 目的が複数ある場合は?
A1: いちばん上位のKPIにつながる目的だけを今回の記事で狙い、残りは別記事で扱いましょう。
Q2: 認知拡大と興味喚起の違いが分かりません。
A2: 認知拡大は「名前を知っているか」、興味喚起は「それが自分に関係ある」と感じてもらえているか、が判断基準です。
ここで決めること:
1. 4つの目的のうちどれを狙うか1つ選んで決める。
2. 選んだ目的をメモや原稿冒頭に明記して、次のステップ(読者理解度の設定)へ進む。
目的を先に固定すると、使うフレームワークが半分以下に絞れ、作業全体がスムーズになります。
ステップ2. 読者の理解度を想像する
文章の目的が決まったら、次は「読者がどこまで知っているか」をざっくり三段階で見立てます。難しく考える必要はありません。以下の目安とセルフチェックを使えば、初めての方でも短時間で判断できます。
初心者レベル
- 製品名や専門用語を聞いたことがない
- そもそも自分の悩みが何か整理できていない
書き方のコツ: まず現状の困りごとを具体例で示し、用語はかみ砕いて解説する
中級者レベル
- 基本用語は理解しているが、メリットの違いが分からない
- 他社製品や代替案を調べながら検討中
書き方のコツ: 機能比較や数値データを提示し、違いを明確に示す
上級者レベル
- 導入手順や費用対効果など具体的な情報を求める
- 失敗事例やサポート体制の詳細が知りたい
書き方のコツ: ROI計算例や導入後のサポートフローを詳しく説明し、不安を解消する
セルフチェック3問
- 読者はその用語を日常的に使う立場か
- 読者は競合サービス名を既に検索しているか
- 読者から導入コストや手順を具体的に質問されたことがあるか
この3問に「はい」が多いほど理解度は高くなります。レベルが分かれば、説明の深さや事例の具体性を調整しやすくなり、読者が「ちょうど知りたかった情報だ」と感じる記事に仕上がります。
ステップ3. 目的×理解度でフレームワークを選ぶ
目的と理解度が決まったら、最適な型は下記のように整理されます。
| 目的 | 理解度 | 適したフレームワーク | ポイント(20字) |
|---|---|---|---|
| 認知拡大 | 初心者 | SDS / AIDMA / PREP | 要点先出しで離脱防止 |
| 興味喚起 | 初〜中級 | PREP / QUEST / AIDMA | 共感と根拠で関心維持 |
| 行動促進 | 中級 | PASO / PASONA / PREP | 課題→解決→CTAを短縮 |
| 販売クロージング | 上級 | FAB / OATH / PREP | 利益と安心で決断促進 |
関連記事:【初心者向け】ランディングページ作成の完全ガイド!現役WEBマーケターが徹底解説!
改善前後でわかるライティング例

実際の業務シーンを想定し、Before(従来文)/After(改善文) を並べて比較します。下の3例を読めば、何をどう直せば読みやすくなるかが一目で分かります。
1. 金属部品メーカー|人事部が「研修費増額」の稟議メール
・Before
退職率が高止まりで若手がすぐ辞めるので離職コストが心配で、来期は社員研修費を150%に増やす案を出したいです。昨年の退職率5ポイント改善という実績があるためこの案を採用していただきたいと思っており、お忙しい中恐縮なのですが今回の研修日増額に納得してもらいたいです。
・After(PREP法を適用:結論→理由→具体例→再結論)
本年度、社員研修費を前年比150%に増額したいと思います。理由は、離職コストを削減し、組織力を底上げするためです。別拠点で試験導入した際は、退職率が5ポイント改善しました。よって、社員研修費の増額こそ人事部の成果を伸ばす最良策だと考えます。
2. SaaS企業|マーケ部がLPの商品紹介セクション用に機能とメリットの訴求文
・Before
当社ツールは自動でレポートが作れることが強みで、担当者の作業時間が浮くし分析も便利で実際に効果が出ています。気軽に機能をお試しいただけるように無料のデモサービスを提供しているので、詳しくは以下のフォームからお問い合わせください。
・After(FAB法を使用:機能→利点→利益)
自動レポート機能がデータを即グラフ化します。手作業を60%削減できて、分析の業務を中断させません。過去5年間の調査によって、毎月60時間分の人件費を節約できることが立証されました。まず無料デモで操作感をお確かめください。
3. コンサル会社 LP|高単価DX支援サービスのクロージング文
・Before
当社のDX支援サービスは実績も多く企業の業務効率を上げられる4四月開始のプロジェクト枠を残り2社に限定しているのですが資料請求フォームの入力項目が多いと言われたり金額が高いという声もあって検討が止まりやすいものの、今なら無料相談も申し込み可能です。このままだと早期導入特典が生かせず機会を逃すことになりそうなのでぜひ検討を前に進めてみませんか。
・After(OATH法を利用:無関心→無感情→思案→苦痛)
現状の業務フローに潜むムダ時間を見過ごしていませんか。そのままでも回ると思っても、毎月の残業代は増え続けます。当社のDX支援サービスなら90日でプロセスを自動化し、投資回収も平均で半年で完了します。4月開始の早期購入特典枠は残り2社のみです。まずは下のボタンから無料相談を予約してください。
4. 機械メーカー LP|「切削事例」ホワイトペーパーDL誘導文
・Before
切削コストを下げる方法を載せたホワイトペーパーを配布しています。高硬度材の加工で時間も費用も無駄が続き資料名の切削事例集2025版を読めば、条件設定も選定方法も分かるので今すぐ多くの方にダウンロードしてほしいと思います。
・After(AIDMA法を利用:注意→興味→欲求→記憶→行動)
高硬度材の切削コストを30%減らせる方法があります。弊社のお役立ち資料「切削事例集」では、工具選定と条件設定を実例でまとめました。このページから最新の切削事例集を無料で入手できます。資料の最新版は「切削事例集2025版」です。以下のフォームに必要な情報を入力して今すぐダウンロードしてみてください。
よくある質問

ライティングフレームワークを使い始めると「ここはどうするの」「この用語の意味は」といった小さな疑問が次々に浮かびます。そこで、実務でよく寄せられる質問を5個に厳選し、1問ずつやさしく解説しました。まずは該当する質問を読んでいただくと、迷いが一気に解消されるはずです。
Q1. 1文が長くなりがちで読みづらいです
1文は40文字を上限に区切り、一文一主張を意識してください。目安として行動を促すCTA周辺はさらに短くし、スクロール中でも内容がひと目でわかるようにします。
Q2. フレームワークを混ぜてもいいのでしょうか
混在はむしろ効果的です。例えば、冒頭をSDSでまとめて全体像を提示し、本文をPREPで深掘りするといった使い分けが読者の負担を減らします。
Q3. データや数値が手元にない場合はどうするか
業界平均や公的機関の統計を引用し、出典を明記すれば客観性を担保できます。オリジナルデータがないからといって数字を避けるより、一次情報に近いデータを補強材料として活用しましょう。
Q4. 記事の最後にCTAを置く場所は固定ですか
原則は末尾ですが、長文記事では途中にミニCTAを挿入し、離脱を防ぐと効果的です。スクロール率が下がる節目に「資料を見る」「詳細を確認する」といった軽めの誘導を挿むとクリック率が向上します。
Q5. 専門用語が多いと初心者は離れてしまいませんか
用語は初出時にカッコ書きで意味を補足し、その後は略称だけを使うと読みやすさが保たれます。説明が長くなる場合は脚注やポップアップで分けると本文がすっきりします。
Q6. 画像や図表はどのタイミングで入れるべきですか
読者が概念を初めて理解する節で図を入れると効果的です。特にQUESTやPREPの具体例パートでは、文字だけでは伝わりにくい流れを図化し、理解を後押ししましょう。
Q7. 行動喚起を強く書くと押し売りになりませんか
読者のメリットをセットで提示すると自然な誘導になります。例えば「無料相談をどうぞ」だけでなく「導入ハードルを整理した改善案を持ち帰れます」と価値を添えることで押し付け感が薄れます。
まとめと次の一歩

本記事では、SDSやPREPなど8種のフレームワークの構造と使い分けを整理し、目的×読者理解度マトリクスで最適な型を選ぶ手順を提示しました。最速で成果を出す近道は「目的を絞る→読者の理解度を見極める→フレームワーク選び→効果測定」の4ステップを守ることです。
ライティングに迷ったら、まずは執筆する目的を考えることから始めてみましょう。TMCデジタルでは、LPをはじめWebサイトの訴求を最適化するための改善案を提案可能です。どうすればユーザーに伝わるのか、どうすればユーザーの行動につながるのか、お客様の立場で丁寧に分析します。フレームワークを使ったライティングに迷ったら、ぜひお気軽にご相談ください。
当サイトでは、LP(ランディングページ)作成の完全ガイドを公開中です。初心者がLPを作成するための流れやポイントをまとめていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。
【初心者向け】ランディングページ作成の完全ガイド!現役WEBマーケターが徹底解説!