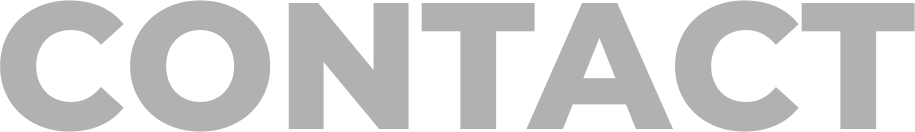専門学校と企業の企業連携(産学連携)事例|TMCデジタルの取り組みを紹介
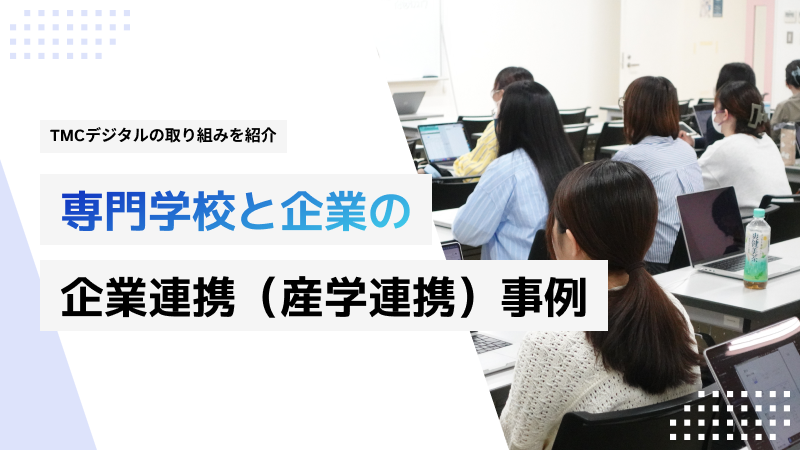
近年、企業と専門学校の連携が注目を集めています。実践的なスキルを学べる専門学校と、実務経験を提供できる企業が手を組むことで、学生は就職前にリアルな職場体験を積み、企業側は新しい発想や将来の人材との出会いを得られるからです。
TMCデジタルでは、学内の授業に参加したり、学生に向けた実務体験プログラムを企画したりといった形で連携を行っています。本記事では、専門学校との取り組みがどのように進められ、教育機関・企業・学生の三方にどんなプラスをもたらすのか、自社の事例を交えながら解説します。
企業連携(産学連携)とは? 専門学校と企業との連携が注目される理由を解説
企業連携(産学連携)とは、教育機関と企業が互いの強みやリソースを交換し合い、学生や業界全体のメリットを創出する取り組みです。企業が実務や最新のビジネス動向を提供し、教育機関が学習環境や専門的な指導体制を用意することで、即戦力づくりや新しい発想の発掘を同時に実現できる点が特徴です。
特に専門学校の場合、実践的なカリキュラムとの相性が良いため、企業連携が進みやすい傾向にあります。学生にとっては現場視点の学びが得られ、企業にとっては若手候補との早期接触が図れるため、お互いがWin-Winの関係を築きやすいのです。
ここでは下記の3つの観点から、その背景を整理しましょう。
- 即戦力となる人材が求められている(実務力・即戦力の育成)
- 若手人材とのマッチングを早期化したい企業側の思惑
- カリキュラムに現場視点を取り込む専門学校の狙い
即戦力となる人材が求められている
DXが進み、海外企業とのグローバル競争が激化するなかで、多くの国内企業は即戦力となる人材を急いで確保しようとしています。専門学校は、職業教育に特化したカリキュラムを設計しているため、学生は実務に直結するスキルや知識を身につけやすい環境にあります。
しかし、いくら教室や校内設備が整っていても、実際の職場が持つ生々しい納期感や顧客対応力までは再現し切れないことが少なくありません。こうした「現場でしか得られないスキル」を獲得するために、企業連携がますます求められているのです。
企業との共同プロジェクトやインターンシップを通じて、学生は変化の速い社会で必要とされるコミュニケーションスキルや問題解決力を、よりリアルに体得できます。たとえば、広告デザインを学ぶ学生なら、実際のクライアント案件で納品までの流れを経験し、クオリティやスピードといった実務の厳しさを学ぶわけです。専門学校の強みである即戦力育成をさらに後押しする仕組みとして、この産学連携が非常に注目されているといえます。
若手人材とのマッチングを早期化したい企業側の思惑
企業としては、優秀な新人を一人でも早く確保し、育成コストを抑えながら戦力にしたいという思惑があります。通常の採用活動は、書類選考や面接を経て内定に至るまで相応の時間がかかりますし、実際に入社してからミスマッチが判明することも少なくありません。
そこで、専門学校との連携によって学生に早期から実務を経験させることで、企業は自社にマッチする人材であるかを見極めやすくなります。
特にITやクリエイティブ系の現場では、ポートフォリオだけでは判断しにくい学生のコミュニケーション力や、プロジェクト推進力が重要になります。実務体験プログラムを金融機関やメーカーが行う例も増えてきており、産学連携の枠組みのなかでインターンシップを拡充している企業は、競合他社より早期に人材を確保できる傾向が強まっています。結果として、「優秀な若手を逃さないために専門学校と手を組む」というスタンスが、業種を超えて広がっているのです。
カリキュラムに現場視点を取り込む専門学校の狙い
専門学校側の視点では、「授業内容をどれだけ実務に近づけられるか」が、学びの質や学生の就職成果を左右します。生徒たちは実際のクライアントワークやプロジェクト進行を知ることで、教科書には載っていない「現場のリアル」を吸収できますし、アクティブ・ラーニングの一環として自己成長を強く実感できます。
たとえば、クリエイターを目指す学生に対して企業が作品レビュー会を開けば、ただの評価にとどまらず、売れるデザインや顧客が求める機能を踏まえた具体的アドバイスを得られます。こうした体験が加わると、学生のモチベーションが格段に上がり、自発的に技術を磨こうとする姿勢が育つわけです。専門学校としても、企業連携の実績を教育の強みとしてアピールできるため、学生募集やブランド力アップにつながります。
このように、専門学校と企業が連携する意図は、「学生に実務感覚を与えたい学校側」のニーズと、「優秀な人材をいち早く囲い込みたい企業側」のニーズにしっかり合致しているのです。次は、TMCデジタルがどのような形で産学連携を実践しているのか、その全体像を詳しく見ていきましょう。
TMCデジタルと専門学校が実践する連携の全体像
ここまで、企業と専門学校の連携がなぜ注目されるかを整理しました。次は、TMCデジタルがどのように協力関係を築き、学生や教職員に具体的な機会を提供しているのかを、プログラムの例を紹介しながら解説します。
TMCデジタルと岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校様との企業連携は、次の3部で構成しました。
- 第一部. 企業紹介・事業紹介セッション
- 第二部. プロジェクト型の課題学習
- 第三部. 各課題の提出物に対するフィードバック
それぞれのステップについて、順番に解説していきます。
第一部. 企業紹介・事業紹介セッション
まず最初に、TMCデジタルが自社のビジネスや事業内容について、学生に直接紹介するセッションを設けます。ここでは、どのような企業理念を掲げているのか、どんなクリエイティブ案件をどのようなクライアントから受注しているのか、普段どのような業務プロセスを踏んでいるのかなど、リアルな現場事例を交えながら分かりやすく説明します。
このセッションを通じて、学生は「業界のリアル」や「自分が目指す職業像」を具体的に描くことができます。また、普段の授業ではなかなか触れられない最新の制作事例や、業界のトレンド、TMCデジタルだからこそ実践できる働き方・クライアントワークへの興味が高まります。
企業側にとっても、自社の強みや独自性、求める人材像を事前に伝えることで、学生とのマッチングの精度を上げるチャンスとなります。
企業紹介では資料を提示しながら先輩社員が丁寧に説明します。
企業連携プログラムは企業を知ってもらう貴重な機会です。パンフレットだけでは伝えきれない自社の魅力をわかりやすく紹介します。
第二部. プロジェクト型の課題学習
次に進むのは、TMCデジタルが用意する「プロジェクト型課題」への挑戦です。実際の業務現場で扱う案件の一部分を担当します。企業によって設定された納期・条件のもと、教職員の指導のもと進行する形式です。学生は自分なりのプランを立て、資料作成やデザイン、企画やアウトプット制作に取り組みます。
このフェーズでは、実務の空気感が強く求められます。単に知識を詰め込むのではなく、スケジュールを管理する能力や納期に合わせてクオリティを追求する姿勢など、現実のプロジェクトを体験できます。さらに、TMCデジタルでは、課題のテーマ自体を複数用意しました。それぞれ違ったアプローチや難易度で実践してもらいます。
学生が取り組んだプロジェクトは以下の3つです。
1. インフォグラフィックの制作
2. Webメディアの記事に設定するMV画像の制作
3. Webページのレイアウト設計〜デザイン制作
第三部. 各課題の提出物に対するフィードバック
学生が制作した課題に対しては、TMCデジタルで活躍する現役クリエイターが、実務目線で詳細なフィードバックやアドバイスを行います。ただ点数や出来映えを評価するだけでなく、どこが「プロの現場で通用する」のか、何を改善すれば「世の中に出せる仕事」へ昇華できるかを、具体的に伝えることを重視しています。
このプロセスは、学生にとって非常に刺激的です。教室内の評価ではなく、本当に世に公開される可能性のある制作物として自分のアウトプットを見つめ直すきっかけになります。また、現役クリエイターとのダイレクトな対話や質疑応答を通じて、自己成長やキャリア選択への自信も育ちます。
事例紹介|TMCデジタル×岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校様のプロジェクトの様子
岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校は、次世代のクリエイターを育成する教育機関です。TMCデジタルをはじめ、Web業界に多数のクリエイターを排出しています。
この章では、TMCデジタルと岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校Webデザイン科様との企業連携プログラムの様子を紹介します。実際に授業やプロジェクトに取り組む学生の姿をお届けします。現場のリアルを知ったり緊張感を経験できることも含めて、企業連携プログラムの醍醐味です。



プロジェクトの説明や打ち合わせは、オンライン形式で開催されました。学生には、自身のPCからオンライン会議に入室してもらいました。本物の案件を扱うということもあり、実際の業務と同様の緊張感に包まれています。

企業連携事業でTMCデジタルが選ばれる理由
TMCデジタルが多くの専門学校や教育機関から企業連携先に選ばれるのには、明確な理由があります。従来の業界説明や事例紹介に留まらない、「本物の現場体験」と「社会に届くアウトプット」の実現こそ、TMCデジタルの大きな特徴です。ここでは、TMCデジタルが支持される主な理由を3つに分けて解説します。
1.「作品が世に出る」リアルな体験を提供
2. 現役クリエイターによる本格的なフィードバック
3. 教育機関・学生・企業の三者にメリットがある仕組み
それぞれの理由について、順番に見ていきましょう。
選ばれる理由1.「作品が世に出る」リアルな体験を提供
TMCデジタルでは、学生が取り組んだ仕事を社会で活用することを重視しています。そのために、学生が取り組んだ課題や制作物を、単に学校内で評価・完結させるのではなく、実際に世に出し、社会で活用できる仕組みを整えています。
たとえば、優秀な制作物は自社メディア、自社サイトなどで実際に使用します。学生にとって自分の仕事が社会へ届くというのは、強烈な成功体験となります。これは、従来型の授業では得られなかった「実際に役立つ手応え」や「大きなモチベーションアップ」へと直結しています。
選ばれる理由2. 現役クリエイターによる本格的なフィードバック
TMCデジタルの連携プログラムでは、現場の第一線で活躍するクリエイター陣が、学生の成果物に対してプロならではの視点でフィードバックやアドバイスを行います。
評価は作品の完成度だけでなく、提案力や改善の可能性といった、実際の制作現場で重要視される総合的な観点から行われます。これにより、学生は学校だけでは得られない「実務の基準」を知り、自分の成長ポイントを明確に把握できます。
選ばれる理由3. 教育機関・学生・企業の三者にメリットがある仕組み
TMCデジタルは、単に企業側の人材発掘や採用を目的とするだけでなく、教育機関に対しても実績に基づいたサポートを提供しています。
カリキュラムへの最新トレンドの取り込みや、成果物の発信による学校広報への寄与が期待でき、学生にとっては実践力と自信を、学校にとっては「就職実績や教育の質向上」という形でWin-Winの関係が築けます。結果として、企業・学校・学生の三者が納得できる実践型連携を実現しています。
このように、TMCデジタルは「リアルな現場体験」×「社会に届く成果」×「本格的なプロの指導」をワンストップで提供できる強みを持っています。これが、数ある企業のなかでもTMCデジタルが選ばれる大きな理由です。
教育機関・学生・企業が得られるメリット
企業と専門学校が連携することで、教育機関・学生・企業の三者すべてに具体的なメリットがもたらされます。それぞれの立場にとっての利点を、以下の通り整理します。
教育機関のメリット
まずは専門学校や大学といった教育機関が得られるメリットを紹介します。
就職実績向上
企業連携は、専門学校の強みである即戦力育成をさらに後押しする仕組みとして有効です。企業連携を実施することで「実際の現場で通用する人材育成」につながります。そのため、就職率や内定先の質の向上が期待できるだけでなく、学校自体の評価や信頼度もアップします。
実務に近いカリキュラムの実現
授業課題やプロジェクトに現場の企業案件や業界トレンドを反映することで、座学だけでは難しいリアルな学びを提供できます。これにより、学生が“即戦力”として社会で認められる土台をつくることができます。
学校ブランディングの強化
実績として「TMCデジタル等との企業連携プログラム」を導入していることを広報・募集活動に活用できます。産学連携を通じて学校のブランド力、時代に合った教育機関としての存在感が高まります。
学生のメリット
次に、実際にカリキュラムを受講する学生にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
ポートフォリオ強化
リアルな案件やプロジェクトで制作した成果物の中には、ポートフォリオに掲載することができるケースもあります。特に、実際に世に出た作品がある場合は、採用時や進学時に大きなアピールポイントとなります。
現場感覚の学習
教科書や模擬課題では得られない、実際の納期・クライアント要求・チーム作業など現場のリアルを経験できます。課題に対する現役クリエイターからのフィードバックも、実践力向上や学習意欲の刺激になります。「作品が世に出た経験」は強烈な成功体験として記憶に残るでしょう。
キャリア観が広がる
産学連携を通じてさまざまな業界や職種を知ることで、進路選択の幅が広がります。企業との接点や現役プロからのアドバイスにより、将来像をより具体的に描くことができます。
企業側のメリット
最後に、企業連携を提供する企業側のメリットを紹介します。
若手人材の発掘・採用
早期に学生と接点を持つことで、自社にマッチした新卒・インターン候補を発掘できます。コミュニケーション能力や実務対応力など、書類選考だけでは分かりにくい本質的な人物像を見極めやすくなります。
企業PR・ブランド強化
企業連携を実施するメリットは、採用活動だけではありません。教育機関との協業実績を自社の広報にも活用でき、企業としての社会的価値や教育貢献につながります。ブランディングや採用広報の面でもプラスの効果が期待できます。
新しい発想の取り込み
学生の柔軟な発想や世代独自の感性は、既存社員にはない新しいアイデアや視点をもたらし、企業のイノベーションをもたらします。プロジェクトへのフレッシュな刺激となり、事業活性化にもつながります。
企業連携プログラムに関するよくある質問(FAQ)
企業連携プロジェクトの実施を検討する際に寄せられる質問とその回答を紹介します。ここでは、以下の3つの質問について見ていきましょう。
質問1. どのような授業内容を提供可能ですか
質問2. 学生の制作物が実際にWeb上に公開された事例を教えてください
質問3. 取り組みについて詳しく質問するにはどうしたらいいですか
質問1. どのような授業内容を提供可能ですか
TMCデジタルの企業連携プログラムでは、次の内容を提供しています。
- デジタルマーケティング業界のトレンド解説
- IT業界で働くリアルな職種の紹介
- プロジェクト形式での課題への挑戦
- 現役クリエイターによる制作物のフィードバック
上記以外にも、授業のカリキュラムやスケジュールに応じて内容の変更が可能です。たとえば、デザインコンペやプレゼン大会など、さまざまな授業を提案いたします。
TMCデジタルが提供する企業連携プログラムには、大きな特徴があります。それは、一方的な授業形式ではなく、実際に本物の案件に取り組んでいただける点です。本物の案件を通じて、現場の納期感や緊張感を味わっていただけます。
質問2. 学生の制作物が実際にWeb上に公開された事例を教えてください
自社が運営するオウンドメディアのバナーや図版、公式サイトのWebページなどです。実際に現場で活躍する現役のクリエイターがフィードバックをするため、プロに負けないクオリティまでブラッシュアップされたものが公開されます。具体的な制作物については、ぜひ、お問い合わせください。
質問3. 取り組みについて詳しく質問するにはどうしたらいいですか
まずはこちらのお問い合わせフォームから、お気軽にご質問ください。授業を担当した経験のあるメンバーが、ご不明点やご質問に回答させていただきます。
プログラムの実施期間やスケジュール、過去の授業内容など、具体的に紹介可能です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
まとめ|TMCデジタルは産学連携で学生のリアルな成長と未来への一歩を応援します
TMCデジタルと専門学校による企業連携プログラムは、学生にとっては教科書だけでは得られない現場のリアルを体験できる貴重な学びの場です。自らの作品が実社会で活用され、現役クリエイターの直接的なフィードバックを受けることで、単なる知識やスキルだけでなく、社会で通用する力まで身につきます。
教育機関にとっては、就職実績や学校評価の向上といった目に見える成果だけでなく、現場で活躍できる即戦力人材を育てるという本来の使命を着実に遂行できる強力な手段となります。また、企業にとっても、若手人材発掘や社会的価値の向上、新たな発想の獲得につながるメリットがあります。
産学連携は、三者すべてがリアルな成果を実感しながら互いに成長できる仕組みです。今後もTMCデジタルは、教育・社会・企業をつなぐ架け橋として、より実践的で価値あるプログラムを提供し続けていきます。